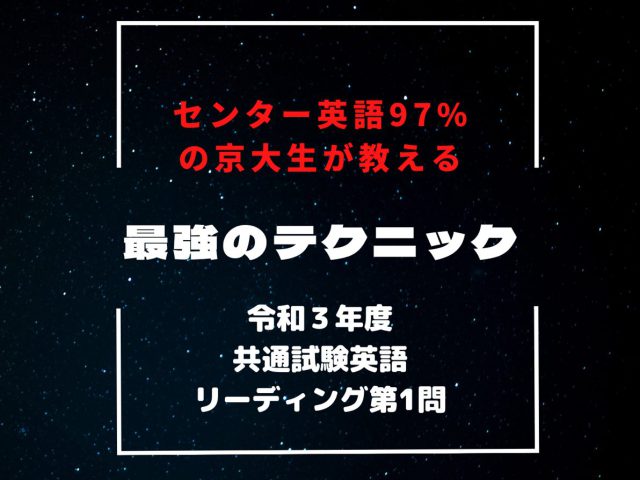不定詞とは何か
不定詞とは準動詞である
不定詞・分詞・動名詞の3つを準動詞といいます。 準動詞とは読んで字のごとく「動詞に準ずる詞(ことば)」です。 簡単にいうと動詞に準ずるわけですから、動詞ではありませんが、動詞に似ているところもあるということです。正確に説明すると、準動詞は動詞としての性格を一定程度保ちながらも、文の要素としての動詞としては機能せず、ほかの品詞の役割を果たすということです。動詞を動詞として用いずにほかの品詞として用いるのが準動詞といってもよいでしょう。to不定詞には何ができるのか
to不定詞の基本用法
① 名詞用法 → S(主語)、O(目的語)、C(補語)になる
② 形容詞用法 → 名詞を修飾する、C(補語)になる
③ 副詞用法 → 名詞以外を修飾する
① 私は毎朝30分走る。(動詞)
② 歩くことは健康に良い。(動詞を名詞に変換)
③ 彼は君に伝えたいことがあるみたいだよ。(動詞を形容詞に変換)
④ 少しでも速く走るために、日々のトレーニングは欠かせない。(動詞を副詞に変換)
あくまで日本語なので正確ではありませんが、to不定詞がなければ②~④の表現形式を失ってしまうことになります。これでは言いたいことも言えません。こんな世の中のせいではありません。ポイズン。
不定詞の動詞的・非動詞的特徴
まず、動詞の特徴について考えてみましょう。動詞の特徴
① 動詞は文型を支配している
② 動詞には必ず主語がある
③ 時制は動詞を変化させることによって表現される
It is necessary to obey the mother.
(母親の言うことに従う必要がある。)
It is necessary for you to obey the mother.
(あなたは母親の言うことに従う必要がある。)
He is said to have obey the mother when he was young.
(彼は若いとき、母親の言うことに従っていたそうだ。)
まず、to不定詞に①の特徴が認められることにご納得いただけるでしょうか。
‘obey’ は他動詞で「~に従う」の意味ですから、目的語が後続していますね。これが自動詞であれば目的語は後続しません。すなわち、to不定詞の ‘to do’ は後続の文型を支配していると言うことができます。勿論、これは主節の文型ではありません。いわば、小さいV、小さいOです。
② 動詞には必ず主語がある、③ 時制は動詞を変化させることによって表現されるについては、次回以降、記事を改めてお伝えします。