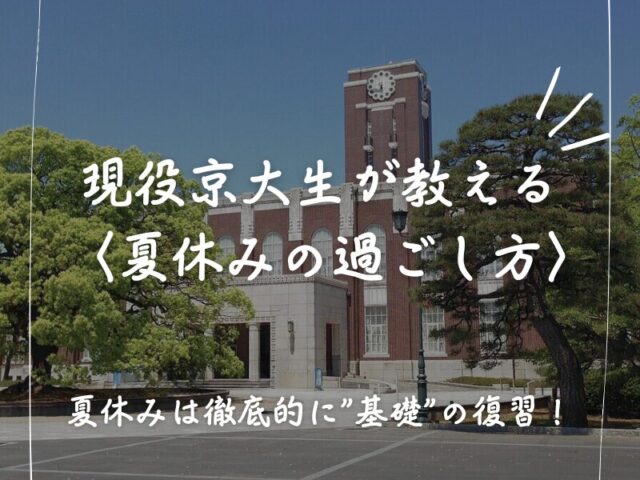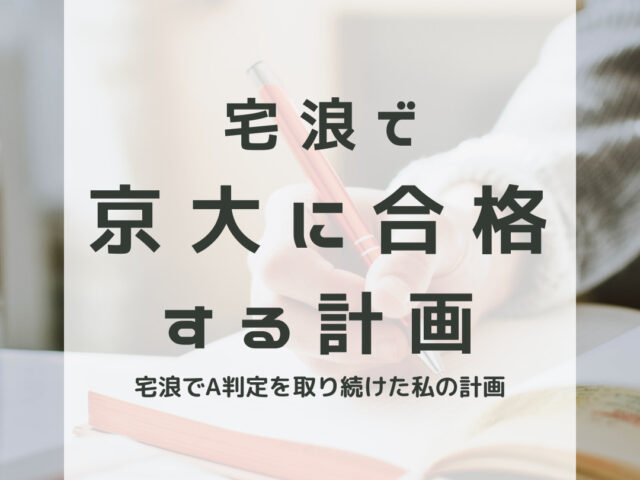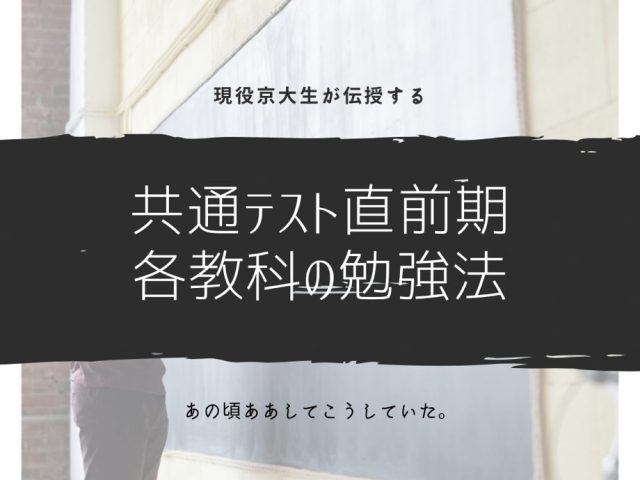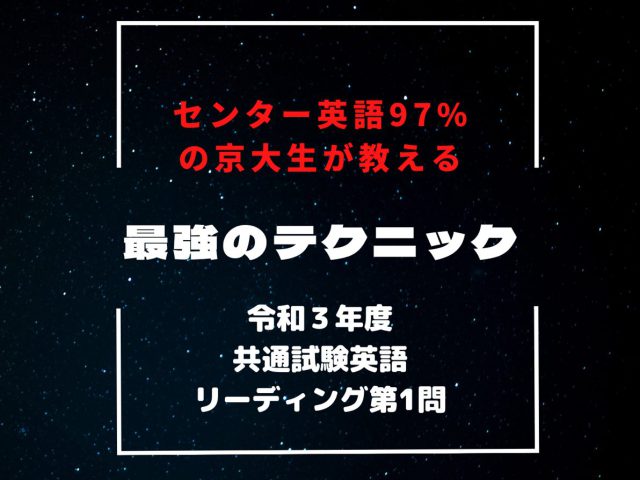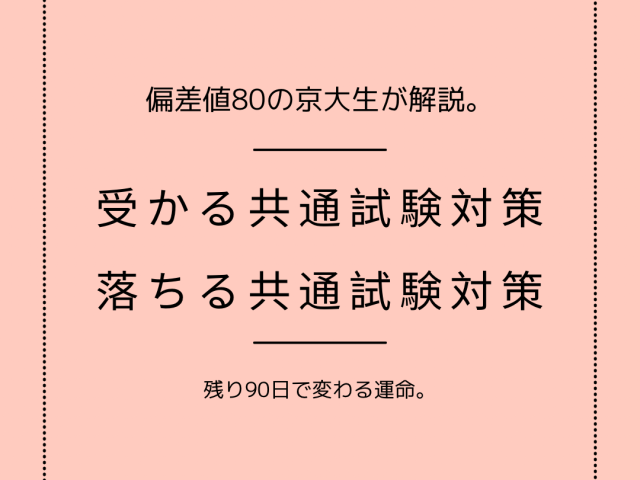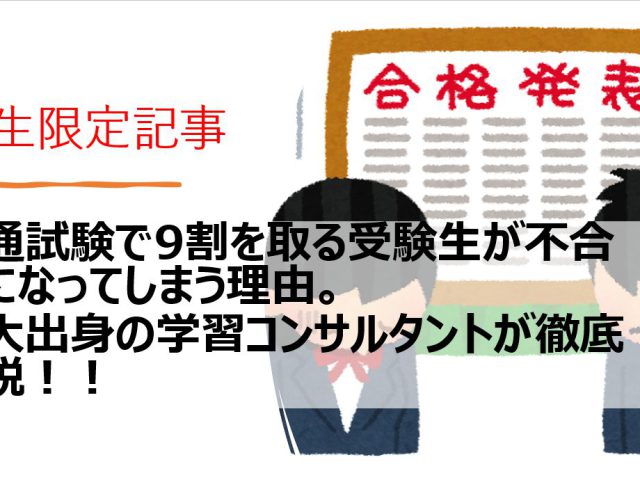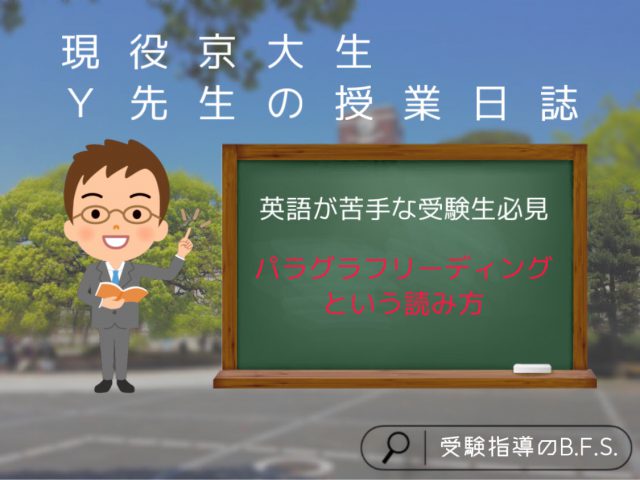丸暗記は頭を悪くする!?
一単語一義主義の弊害
「始めたばかりのうちは、単語の意味を一つに絞って覚えよう!」こんなアドバイスを受けたことはありませんか?このアドバイスはどこか体育会系的で、アドバイスをする当人の迫力をも掛け合わせると、謎の説得力があります。しかし、この方法では到底覚えられませんし、脳をいたずらに傷つけて頭を悪くさえします。語学は確かにトレーニングの側面が強いのですが、頭を使わないトレーニングをしても成果は見込めません。脳はネットワークを求めている!
以下に羅列する文字列を暗記しないといけないとなったら…sitzen – sit
werben – recruit
heben – raise, lift
Saepe – しばしば
bonus – よい
柿本人麻呂 – かきのもとのひとまろ
ツルゲーネフ – ツルネーゲフ
住む – 通う
けし – 異様だ
享楽 – 楽しみにふけること
デカルト – 『方法序説』、『省察』
こうなると考えることをやめてすぐに丸暗記に走る猿が現れます。数が限られていれば、その場しのぎでは覚えられるからです。次の日には忘れています。繰り返しぼそぼそと声に出して、しこしこ覚えるわけです。これは適切な知のあり方ではありません。ただの奴隷状態です。そんなことって許せますか?覚えないといけないことを突き付けられて、丸暗記という脳の酷使を強いられるわけです。暗記の得意な人、頭の良い人はここで脳の負担を減らす工夫をします。それは語同士のネットワークを作ることです。
情報量が多い方が覚えやすい?
例を変えて考えてみましょう。人の顔と名前が一致しない。入学したての頃はクラスメイトが誰が誰だかは分かりませんよね。先生からしてもそうです。さあここに名簿があります。この名簿を念仏のように唱えて丸暗記するほど頭が悪いことはないでしょう。
相星 創吾
赤松 健太郎
飯田 夏実
池田 輝樹
池田 佳代子
………
これがあと30回以上続くとなると、気が遠くなりそうですね。ですが、しばらくするとすっかり覚えられてしまいます。毎日接しているということに加えて、それぞれについて情報が増えているということが確認できます。情報量が増えると記憶が安定するのです。
相星 創吾 – 野球部なのに長髪
赤松 健太郎 – めっちゃ真面目
飯田 夏実 – ガタイが良いことを気にしている
池田 輝樹 – 学校にあまり来ない
池田 佳代子 – 快活でいて頭もよい、部活!勉強!って感じ
さらに、ここにキャラクター同士の関係性を加えると、ネットワークができ、相補的な記憶の頑丈な網が完成するのです。こういうのを語彙について当てはめたとき、それをメンタルレキシコンと言います。「犬」といえば「忠実」、「犬」の反対(?)は「猫」などといった語と語との何らかの関係性の総体のことです。