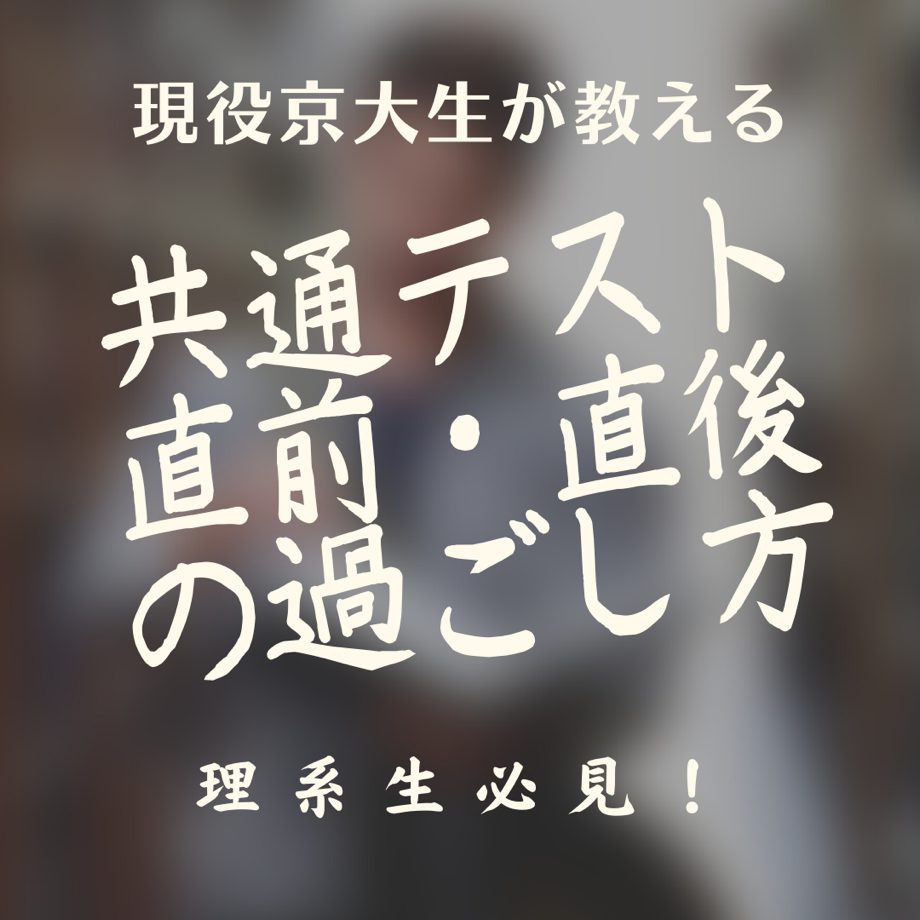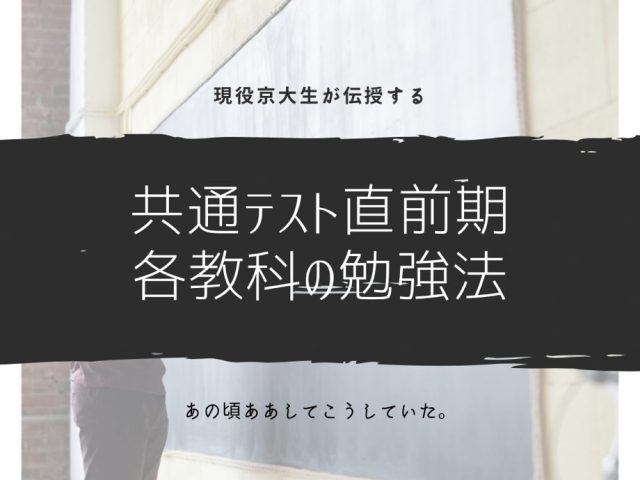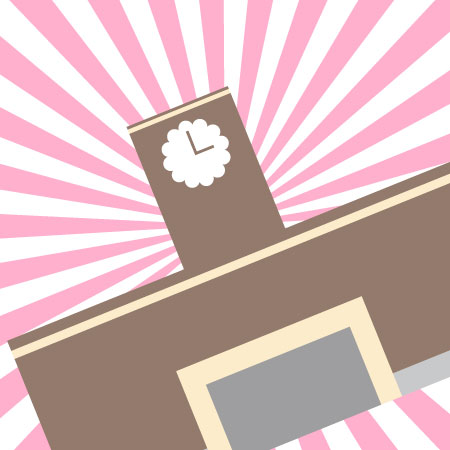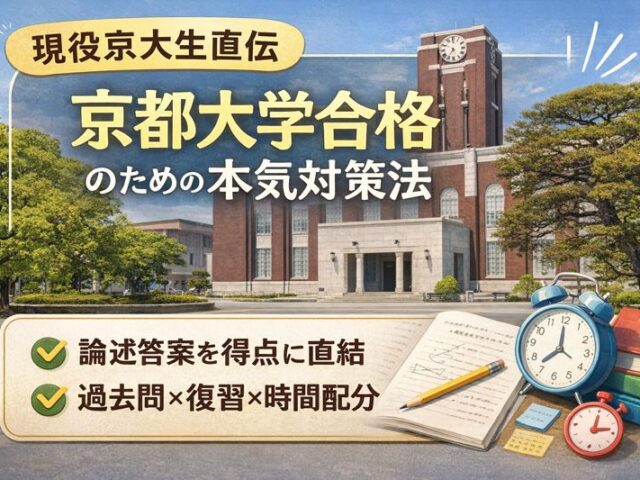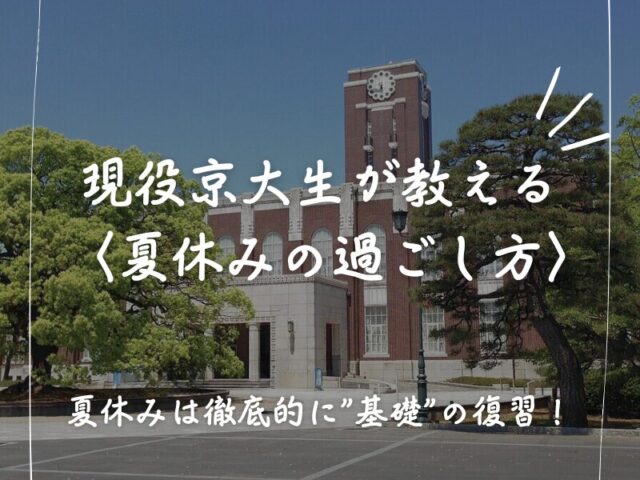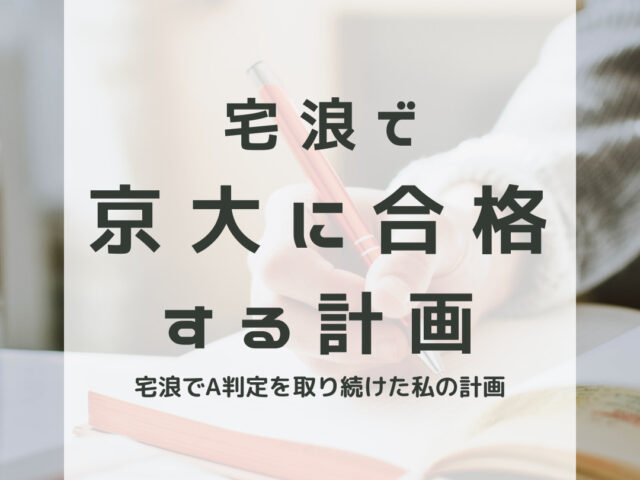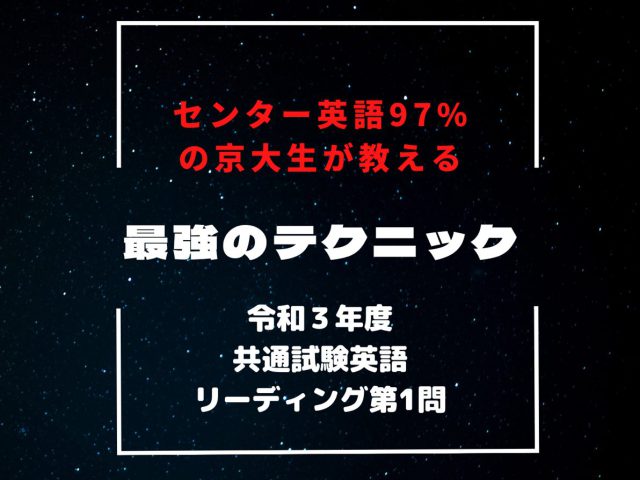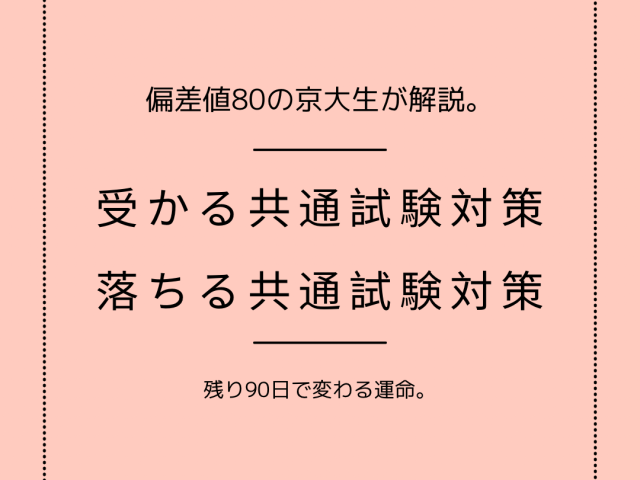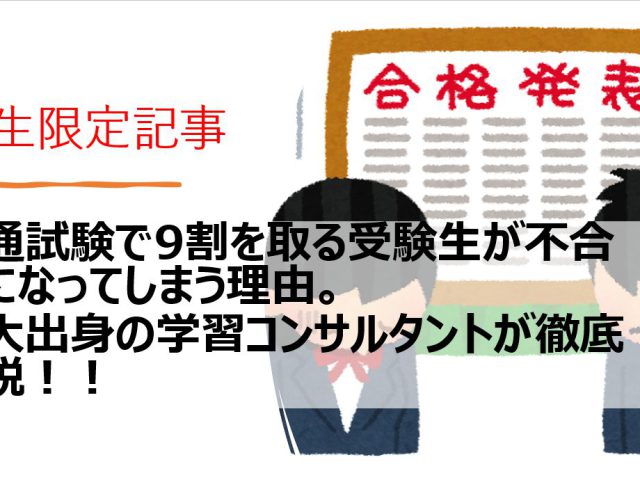目次(クリックで該当箇所へ移動)
共通テストまでの計画を立てる指針
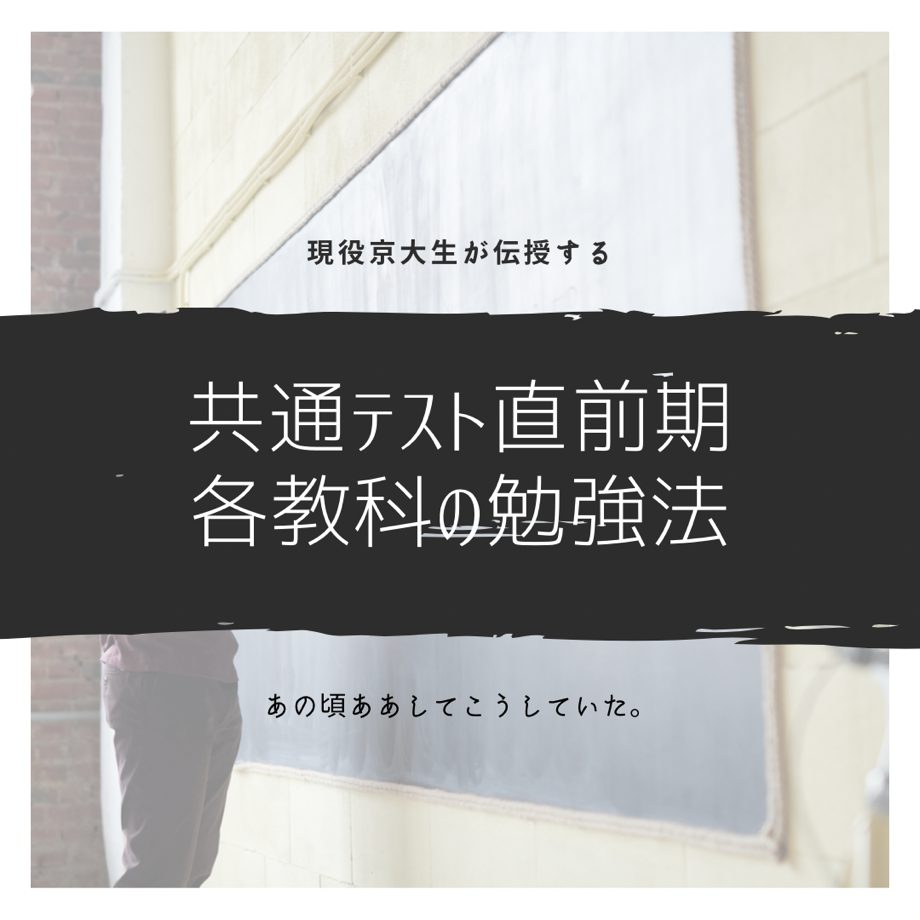 まず共通テストと2次試験の配点の割合は大学によって大きく異なるため、ご自身の受験される大学の配点から戦略を立てることが大事です。それを踏まえた上で、それぞれの科目について振り返っていこうと思います。
まず共通テストと2次試験の配点の割合は大学によって大きく異なるため、ご自身の受験される大学の配点から戦略を立てることが大事です。それを踏まえた上で、それぞれの科目について振り返っていこうと思います。
筆者の受験タイプ
私は京大の理系学部を受験する予定だったために、共通試験で受験する教科としては社会、国語、英語の点数が加算されました。
受験生
ということは基本的には文系教科の対策が、共通テストにおける対策の中心となるわけですね!
国語
元々得意であり、かつ本番での点数の不確実性が大きいため学習時間のウェイトは小さかったです。国語はほかの教科と比べて点数の変動が極めて大きい科目であるため、その振れ幅をできるだけ小さくするために過去問を多く解きました。 古典は十二月頃から単語と文法の暗記を重点的にしました。特に漢文は暗記事項が少なく点数効率がよいのでおすすめです。
受験生
確かに残り限られた時間の中では同じ”国語”であっても、テクニックを追求しないといけない現代文よりも、知識をinputする対策が中心の古典に力を注いだ方がコスパが良いですね!
英語
一番の得意科目であったためほとんど対策に時間をかけていませんでした。自分の得意科目は点数が落ちないくらいにとどめておいて苦手科目の勉強を重点的にした方が点数は上がりやすいです。英語はとにかく時間との闘いなので時間を計って一回分を一気に解く練習をしていました。
受験生
文系教科の対策が中心とはいっても、自分が得意な教科であれば、それに費やす時間を苦手な教科や未対策の教科に費やすことが得策ということですね!
数学
計算ミスが多かったため1回1回計算ミスがないか軽くチェックすることを日頃からしていました。時間がなくついつい焦ってしまいますが、計算ミスによって大問ごと点数がなくなることも珍しくないため、そこにこだわりました。2次試験の勉強にもなるように、自分が特に点数の低い傾向にある単元を重点的に演習しました。 納得の受験生
受験生
過去問演習というよりかはケアレスミスによる失点の予防と、二次試験の対策も兼ねられる苦手単元の演習に時間を費やされたのですね!
物理
時間が足りないことはなかったため、問題集を使って単元ごとの演習をしました。2次試験と違い問題の流れに乗る必要があり、やりにくいことが多いためそれに慣れるのを意識していました。また共通テストからは思考力を問う問題として、見慣れた典型問題とは違った視点や思考で解かなければいけない問題があったためそれを重点的に演習しました。問題を見て瞬時に解法が出てくるくらいでないと検算までは終わらなかったため大問1つ12分で解く練習をしました。
受験生
二次試験の出題とは顕著に違いがある部分を中心に対策をされたのですね。確かにこれまでの二次試験の学習だけでは対策しきれていなかった部分は失点につながりかねない箇所ですね…
化学
物理と同じく単元ごとに勉強しました。二次ではあまり出ない実験器具の使い方の問題やマニアックな知識問題が出るためそれを重点的に勉強しました。参考書よりも学校の教科書や資料集の方がその辺については詳しく書いてあるのでおすすめです。加えて化学は特に計算ミスが多発する科目の1つであるため、二回計算するなどして対策していました。 納得の受験生
受験生
数学と同様に計算ミスが発生しやすい教科については抜かりなくその対策をされているのですね。受験は1点を争う戦いなので見習うべき姿勢です!
倫理・政治経済
赤シートで隠し、何回も声に出しながら用語を暗記しました。とにかく声に出すことで目で見るだけよりも確実に覚えられると思います。また、友達と問題を出し合ったりアプリを活用したりして、一問一答形式を繰り返すのが楽しく覚えられてよかったです。
受験生
声に出して暗記する学習は効果的なのですね!またアプリなども使用されていたとのことで試してみます!
終わりに
当時を振り返り共通テストまでの各教科の勉強計画とその指針についてお話しました。特に国公立を受験される受験生は共通テストと二次試験との勉強の配分なども気になるポイントかと思われますので、是非当記事を参考にしてみて下さい。学習相談をしたい
受験指導のB.F.S.には京都大学の受験を突破した講師が約200名在籍しております。いうまでもなく、受験の勝ち方に精通した講師ばかりです。精通しているということは、計画の立て方やモチベーションの維持の仕方まであらゆることをアドバイス可能となっています。いま受験勉強に関してお悩みのある方は是非お問い合わせ下さい。お問い合わせは下記フォームから!Webフォームで問い合わせる
LINEで問い合わせる
3日以内に担当者がメール/LINEにてご返信いたします。
LINEで受験相談
また簡単に受験相談やサービスのご相談をされたい方はB.F.S.のスタッフとLINEにてやり取り可能となっております!その他の受験記事