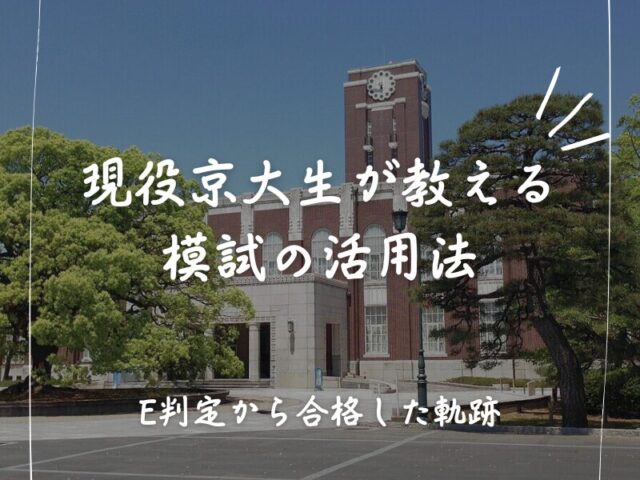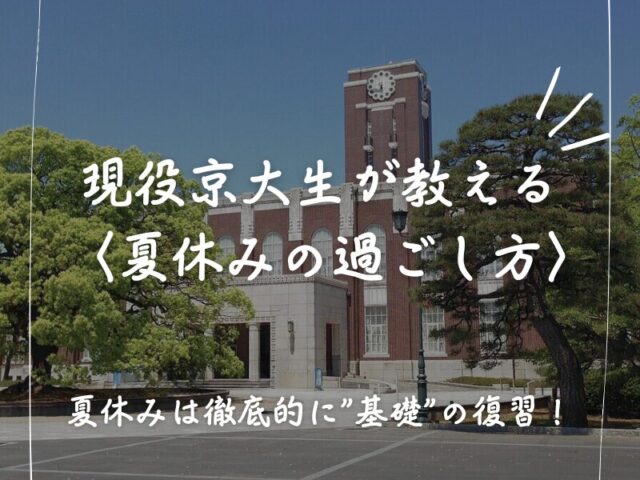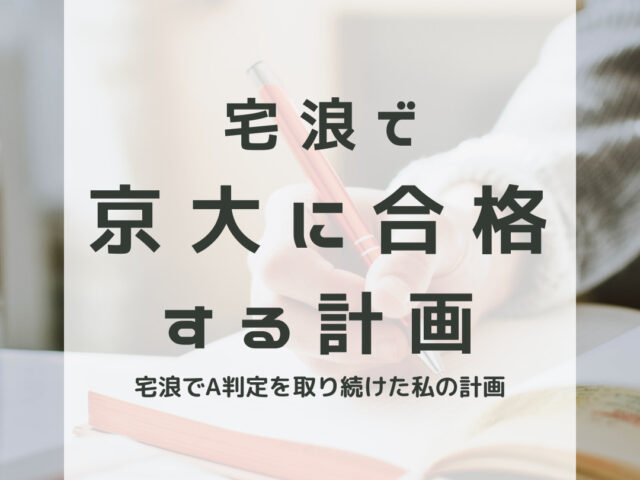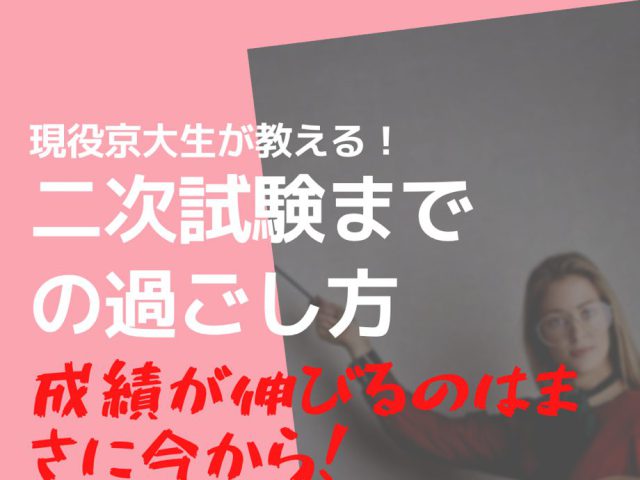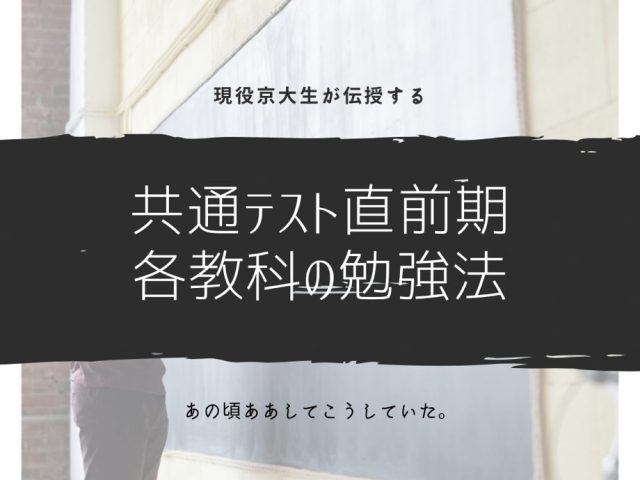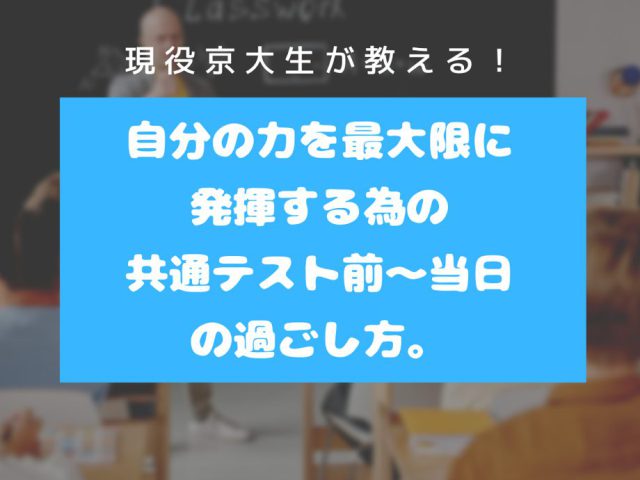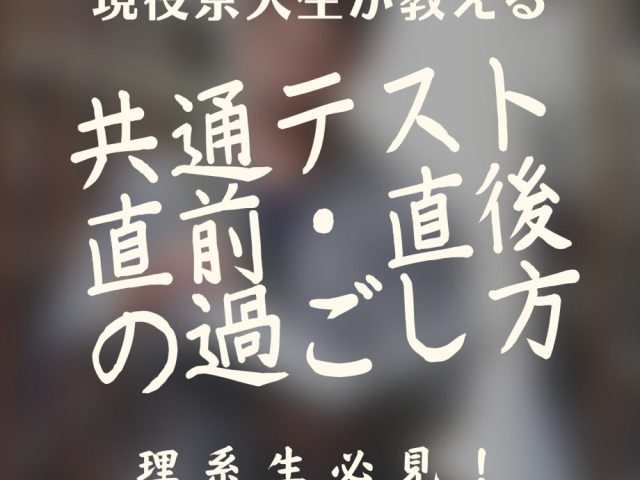16時30分【現代文】
次は現代文です。時間がない受験生は現代文の勉強を蔑ろにしがちですが、きちんとした考え方と方法で対策を行えば、時間の無駄にはなりません。私の考えですが、現代文においては「問題演習をどれだけするか」ではなく、「どのように問題演習をするか」の方が大事です。現代文についての記事も書いていますので、ぜひ参考にしてください。(※現代文についての記事はコチラ『偏差値80の京大生が教える『センター現代文9割突破の必勝法』ー設問へのアプローチ法 編ー』)勉強内容は以下の通りです。
- 二次試験の問題演習 90分
18時00分【古文】
次は古文です。古文もある意味で英語と同じで、知識をインプットして、しっかりとアウトプットする練習が必要です。勉強内容は以下の通りです。
- 単語学習 30分
- 問題演習 60分
19時30分【地理】
次は地理です。1日も終盤に差し掛かり、お腹も減り集中力も途切れかけるこの時間帯に、自分の好きな教科の学習をしていました。地理は、日本史と違いアウトプットが大切です。4月〜9月くらいまで集中的にインプットを行い、秋以降は専らアウトプットの練習=センター試験演習を行っていました。勉強内容は以下の通りです。
- センター試験過去問演習 90分
20時30分【生物】
私が受験生当時は、今とは違って基礎科目が2つではなく、理科が1教科でした。 生物Ⅰに関しては、知識力と論理力を試す問題が半分ずつ位であったので、対策も半分ずつ取っていました。勉強内容は以下の通りです。
- 知識のインプット 45分
- 問題演習 45分
22時00分【漢文】
1日の最後は漢文です。総得点に占める配点も非常に低く、対策へのやる気もあまり湧かない教科だったので、「今日もこれで終わりだー!」と感じられる最後に持ってきました。勉強内容は以下の通りです。
・知識のインプット 30分
22時30分 勉強終了
長い長い1日もようやく終わりました。今考えると、ゾッとするくらい勉強していますが、当時は気がつけばこんな時間になっていました。休憩自体もほとんど行っていませんでした。ある意味で、好きな教科の勉強をしている時間が息抜きの時間のように感じていました。しかし、そう感じられない人も多くいると思います。休憩なしでぶっ通しでやる事は体力や精神面でもしんどいと思います。従って、こまめに休憩を確保して下さい。ただし、サボるための休憩ではなく、勉強のための休憩となることを忘れない下さい! 実際、4月から毎日このようなスケジュールで勉強していたので、受験本番では自分に自信がかなりありました。自分はこんだけやっただ。席の周りにいる人よりも確実にやってきた。故に「勝てる!」そう思えました。 受験本番であなたを救うのは、あなたが辿ってきた軌跡です。まとめ
以上が私が受験生であった時の、11月の1日のスケジュールです。二次試験とセンター試験の過去問演習との両立も難しく、何が正解で何が間違っているかも分からず、不安になっている方も多いかと思います。しかしながら唯一の正解はありません。あなたにあった最適なスケジュールを作ってください。 受験指導のB.F.S.へのお問い合わせは以下よりお願い致します。サービスの紹介ページはこちらから。Webフォームで問い合わせる
LINEで問い合わせる
3日以内に担当者がメール/LINEにてご返信いたします。